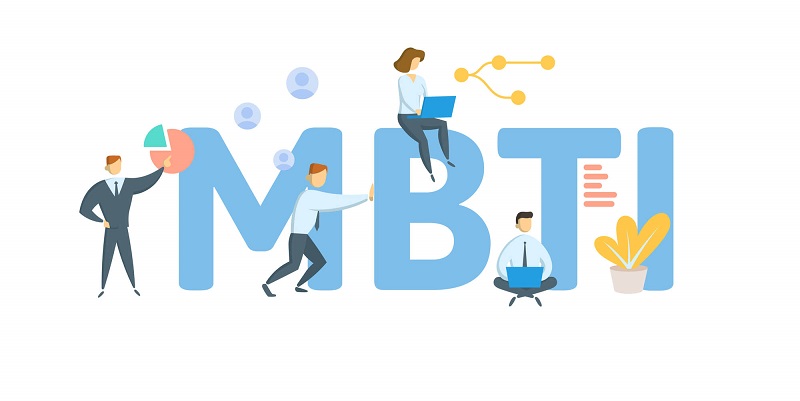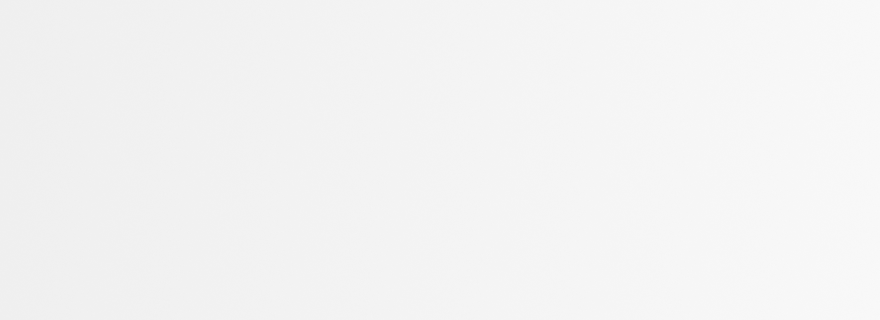目次
クルマの電動化(EV)や自動運転技術が急速に進化する一方で、その最先端技術を支える自動車整備士の人手不足が深刻化しています。その結果、整備士の価値は高まり続け、平均年収はこの5年で+17万円以上も上昇していると言われています。
「資格を取るのは大変そう…」「未経験からでもなれるの?」
そんな疑問や不安を抱えるあなたのために、この記事では「①資格の種類」「②受験までのルート」「③合格率と費用」「④自分に合った勉強法」「⑤キャリアと年収」の5つの軸で、自動車整備士資格のすべてを徹底解説します。
あわせて「学校なしで資格は取れるのか?」「合格率はどのくらい?」「年収は上がる?」といったよくある質問にも答えているので、未経験者の方でも安心して読み進められるはずです。
記事の最後には、受験スケジュール早見表と勉強計画チェックリストもご用意。最短でプロの整備士になるための道筋が、この記事一本で明確になります。未来のクルマ社会を支える、やりがいと安定に満ちたキャリアへの第一歩を、ここから踏み出しましょう。
【関連記事】自動車工場勤務はきつい?仕事内容・年収・向いている人を解説!3Kイメージの真実と高収入求人の選び方
1. 自動車整備士の資格は何種類ある?1級・2級・3級と専門分野の違い

自動車整備士の資格はレベルや専門分野によって細かく分類されています。この章では、それぞれの等級や違い、未経験者におすすめのルートまでをわかりやすく解説します。
レベル別:1級・2級・3級の違い
資格は1級・2級・3級の3段階に分かれていて、それぞれ対応できる作業内容や責任の範囲が異なります。
3級自動車整備士:基本の「き」
タイヤ交換やオイル交換など、基本的な整備作業の一部を担当できます。ただし、エンジンやブレーキといった重要部品の分解整備は単独ではできず、2級以上の整備士の監督下で行う必要があります。未経験者が最初に目指す入門的な資格です。
なお、3級整備士は独学でも取得可能とされていますが、実技対策や法令知識が問われるため、講習や通信講座の活用が推奨されます。
2級自動車整備士:現場の“主役”
自動車整備の中心となる資格で、ほとんどすべての分解整備を一人で行うことができます。自動車整備工場で働く整備士の多くが、この2級資格を保有しています。就職や転職において、実質的なスタートラインと言える最も重要な資格です。
1級自動車整備士:最高峰の“エキスパート”
2級の範囲に加えて、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)などの先進技術に対応できる高度な知識と技術を持つ証明です。他の整備士への指導や、工場の安全管理など、リーダーとしての役割も期待される最高峰の資格です。
専門分野別:ガソリン・ジーゼル・シャシなど
さらに、扱う車種や専門分野によって資格が細かく分かれています。
| 資格区分 | 主な対象車種・業務内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自動車シャシ整備士 (3級) | タイヤ、ブレーキ、サスペンションなど、車の足回り部分の基本整備。 | ガソリン・ジーゼル問わず整備できるため、最初の取得におすすめ。 |
| 自動車ガソリン・エンジン整備士 (3級/2級) | 一般的な乗用車(ガソリン車)のエンジン整備。 | 最も需要が高く、一般的な整備工場やディーラーで必須の資格。 |
| 自動車ジーゼル・エンジン整備士 (3級/2級) | トラックやバスなど、ディーゼル車のエンジン整備。 | 運送会社やバス会社の整備工場などで専門性を発揮できる。 |
| 二輪自動車整備士 (3級/2級) | オートバイ(バイク)の整備。 | バイク好きにはたまらない、趣味と実益を兼ねた専門資格。 |
| 自動車電気装置整備士 (3級) | バッテリー、エアコン、カーナビなどの電装系の整備。 | 近年の自動車の電子化に伴い、需要が高まっている。 |
| 自動車車体整備士 (3級) | 事故などで損傷したボディの板金・塗装・修理。 | 修理技術に特化した専門職。美的センスも求められる。 |
ポイント
未経験から目指すなら、まずは「3級自動車シャシ整備士」を取得し、その後、実務経験を積みながら現場で最も需要の高い「2級ガソリン自動車整備士」を目指すのが王道のルートです。
実務経験を重ねることで、1級や電装系など上位資格の受験資格も得られるようになります。キャリアアップを見据えるなら、計画的なステップアップが大切です。
【関連記事】工場など製造業におすすめの資格ランキング
2. 自動車整備士になるには?学校卒と実務経験ルートの違い

自動車整備士になるためには、国家資格の取得が必須です。ここでは、専門学校に通うルートと、実務経験を積んで取得するルートの2パターンを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
ルート①:専門学校に通う“最短・確実”ルート
国土交通大臣が指定する「自動車整備士養成施設(専門学校や職業訓練校など)」に通う方法です。
メリット
- 【実技試験が免除に!】 卒業と同時に2級または3級の実技試験が免除され、学科試験に合格すれば資格を取得できます。これが最大のメリットです。
- 【最短で2級を取得可能】 2年制の養成施設を卒業すれば、実務経験なしで2級の受験資格が得られます。
- 【就職に圧倒的に有利】 学校に多くの求人が集まり、就職サポートも手厚いです。
デメリット
- 【学費がかかる】2年間で200万円~250万円程度の学費が必要です。
- 【通学時間が必要】日中に学校に通う必要があるため、働きながら学ぶのは難しいです。
ルート②:実務経験を積む“現場たたき上げ”ルート
未経験OKの認証工場や指定工場(いわゆる町工場やディーラーなど)に就職し、働きながら受験資格を得る方法です。専門学校に通わなくても整備士資格を取得することは可能ですが、実務経験が必須となるため、時間と計画性が求められます。
メリット
- 【給料をもらいながら学べる】学費がかからないどころか、収入を得ながら実践的なスキルを身につけられます。
- 【自分のペースで進められる】学校に通う必要がないため、年齢やライフスタイルを問わず挑戦できます。
- 【未経験でも始められる】未経験からでも応募できる求人が多く、特別なスキルや資格がなくてもスタートできます。
デメリット
- 【受験資格を得るまでに時間がかかる】3級を受験するのに最低1年の実務経験、2級を受験するには3級合格後にさらに3年の実務経験が必要です。
- 【実技試験がある】実技試験を自力で対策する必要があり、合格のハードルが上がります。
- 【勉強時間の確保が大変】仕事で疲れた後に、学科の勉強時間を自分で確保する強い意志が必要です。
| ルート | 2級ガソリン取得までの最短期間 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 専門学校ルート | 2年 | 実技試験免除、就職に有利 | 学費が高額、通学時間が必要 |
| 実務経験ルート | 4年以上(3級1年+2級3年) | 給料をもらいながら学べる、学費不要 | 時間がかかる、実技試験の対策が必要 |
3. 【2025〜26年最新版】自動車整備士試験の合格率・受験料・試験日まとめ

「どのくらいの合格率?」「受験料はいくら?」「試験日はいつ?」といった受験にまつわる疑問にすべて答えます。最新データをもとに、資格別の合格率・受験料・試験時期を一覧で紹介します。
合格率の目安
3級自動車整備士
- 合格率は学科・実技ともに60~80%の範囲で、近年はおおむね70%前後となっています。
- 令和4年度~令和6年度の平均値では、ガソリン71.4%、ジーゼル59.1%、二輪84.9%、シャシ65.2%などです。
- 独学の社会人など、受験者の背景によって難易度に差はありますが、3級は比較的チャレンジしやすい資格といえます。
2級自動車整備士
- 学科試験の合格率は種類ごとに異なり、おおむね60~90%が目安。
- 実技試験の合格率は20~40%程度と学科に比べてやや低く、受験機会も少ない年がある。
- 自動車整備の専門課程を修了して受験する学生の合格率が高いのが特徴。とくに実技試験は独学での対策が難しいため、通信講座やスクールの利用を検討する受験者も増えています。
1級自動車整備士
- 筆記試験の合格率:近年は53%~66%(令和6年度は65.7%、令和5年度は59.1%、令和4年度は53.0%)。
- 実技試験の合格率:31.9%~64.3%と年度でばらつきあり。直近では32%前後。
- 口述試験の合格率:毎年95%~98%と非常に高い。
2級、3級は、しっかりと勉強すれば十分に合格が狙える難易度です。1級は全体として合格率が低い狭き門であり、学科・実技・口述すべてに合格する必要があります。総合的な合格率は20%程度と言われることもありますが、年度や受験者層によって変動します。
受験料と試験日(登録試験)
自動車整備士技能登録試験は、学科試験のみで、年に2回(通常は9月~10月と2月~3月)実施されます。地域によって若干前後するため、受験予定の都道府県の整備振興会サイトも必ず確認しましょう。
| 資格区分 | 受験手数料(学科) |
|---|---|
| 1級小型自動車 | 10,000円 |
| 2級ガソリン・ジーゼル | 7,200円 |
| 3級シャシ・ガソリン等 | 5,200円 |
| 自動車電気装置 | 5,200円 |
| 自動車車体 | 5,200円 |
(出典:日本自動車整備振興会連合会)
※上記は2025年時点の目安です。最新の情報は必ずJASPAの公式サイトでご確認ください。
4. 独学・通信・専門学校…勉強法と費用を徹底比較
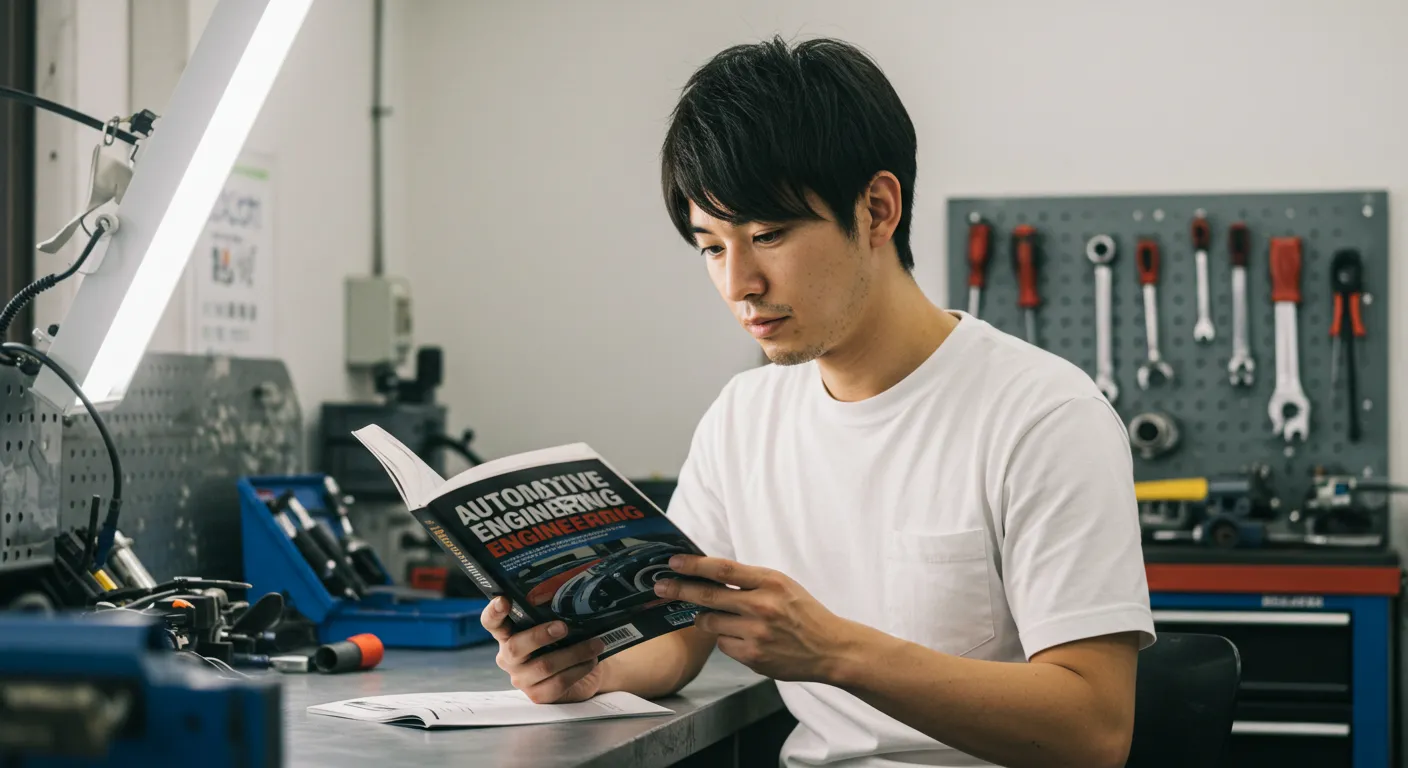
自動車整備士の資格を目指す方法には、独学・通信講座・専門学校の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のライフスタイルや目標に合わせて選ぶことが大切です。
1. 独学
- メリット: 費用を最も安く抑えられる(教材費1万円程度)。自分のペースで学習できる。
- デメリット: モチベーション維持が難しい。質問できる相手がいない。実技試験の対策が困難。
2. 通信
- メリット: 独学より効率的に学べる。質問サポートなどがある。費用は独学と専門学校の中間(5万円~15万円程度)。
- デメリット: 実技試験の対策は別途必要。強制力がないため、自己管理能力が問われる。
3. 専門学校
- メリット: 実技試験が免除になる。合格率が非常に高い。同じ目標を持つ仲間と学べる。
- デメリット: 費用が最も高額(200万円以上)。通学が必要。
学習スタイル選びのヒント
時間と費用に余裕があるなら専門学校が最も確実。働きながら最短で目指したい人には、通信講座の活用に加えて、職場の先輩に実技を見てもらう方法が現実的です。
5. 整備士のキャリアと年収は?町工場・ディーラー・メーカーを徹底比較

資格を取得すると、キャリアと年収はどう変わるのでしょうか?自動車整備士として働く場所によって、収入もキャリアの広がり方も大きく変わります。この章では代表的な4つの職場パターンを比較し、将来的なステップアップの選択肢も紹介します。
| 働く場所 | 特徴 | 年収目安(2級保有者) |
|---|---|---|
| 民間整備工場(町工場) | 様々なメーカーの車種を扱う。幅広い知識と応用力が身につく。アットホームな雰囲気。 | 350~550万円 |
| ディーラー | 特定メーカーの車種に特化。最新技術や接客マナーを学べる。福利厚生が手厚い傾向。 | 400~650万円 |
| 自動車メーカーの工場 | 完成車の最終検査、試作車の開発・実験、品質保証など。整備士の知識を活かせる専門職。 | 450~800万円以上 |
| その他 | カー用品店、ガソリンスタンド、運送会社、保険会社(アジャスター)など、活躍の場は多様。 | - |
取得した資格は、転職市場での評価や収入アップに直結します。例えば、無資格で年収300万円だった人が、2級整備士資格を取得しディーラーに転職して年収450万円になる、といったケースは珍しくありません。
最近では経験者採用に加え、実務経験が浅くても応募可能な求人も増えています。ディーラーなどで培った整備経験を活かし、メーカー側で新車の品質保証部門や、開発中の実験車両の整備・評価といった、より専門的で待遇の良い仕事に就く道もあります。工場求人ワールドでは、こうしたメーカー系の求人も扱っており、キャリアの可能性を広げることができます。
6. よくある質問|資格の難易度・実技免除・EV整備の資格は?

Q1. 自動車整備士の資格って、どれくらい難しいんですか?
A1. 2級・3級の学科試験の合格率は60~80%と比較的高く、真面目に勉強すれば決して難しい試験ではありません。最大の壁は「実務経験の年数」と「実技試験」です。専門学校ルートなら実技が免除になるため、難易度はぐっと下がります。
Q2. 自動車整備士3級は、独学でも取れますか?
A2. はい、可能です。実務経験を1年以上積めば、3級の受験資格を得られます。教材費1万円ほどで独学もできますが、実技対策が難しいため、通信講座や先輩整備士のサポートを受けるのがおすすめです。
Q3. 働きながら2級整備士を取得するには、どのくらいかかりますか?
A3. 最短でも4年程度かかります(3級取得に1年、2級取得にさらに3年の実務経験)。ただし、実務ルートなら収入を得ながら学べるという大きなメリットがあります。
Q4. 実技試験が免除になる条件を詳しく教えてください。
A4. 国が指定した「自動車整備士養成施設(=専門学校など)」を卒業することで、該当する級の実技試験が免除されます。また、認定工場で働きながら技術講習を受講した場合(いわゆる「二種養成施設」修了)、同様に免除されます。
Q5. EVやハイブリッド車を整備するのに、特別な資格は必要ですか?
A5. はい、必要です。高電圧のバッテリーを扱うため、「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が義務付けられています。これは1日で修了できる講習です。さらに専門性を高めるための「一級自動車整備士」や、各メーカー独自の資格もあります。今後、EVの普及に伴い、これらの資格を持っていると、キャリアアップにも有利です。
Q6. 通信講座で資格を取ることはできますか?
A6.通信講座は、学科試験対策に非常に効果的です。ただし、実技は含まれていないため、別途工場での実務経験を積む必要があります。ユーキャンや日建学院などの講座が有名です。
7. まとめ|今すぐ始めるチェックリスト&学習スケジュール表

ここまでで、自動車整備士資格の全体像と取得方法が見えてきたはずです。最後に、今すぐ行動に移すためのチェックポイントと学習スケジュールのヒントをお届けします。
整備士資格まとめ|5つのポイント
資格の種類
3級(入門)、2級(現場の主力)、1級(エキスパート)のレベル別。ガソリン・ジーゼルなど専門分野別にも分かれる。
取得ルート
「専門学校(最短2年・実技免除)」か「実務経験(4年以上・実技あり)」が基本。
難易度と合格率
2級・3級は国家資格の中では比較的取得しやすく、合格率も高い。
将来性
EV・自動運転時代に整備士のニーズと価値は上昇中。年収アップと安定したキャリアが期待できる。
キャリアパス
ディーラーや町工場だけでなく、メーカーの工場など、活躍の場は幅広い。
最短ルートで資格取得を目指す!アクションプラン
1. 自己診断&ルート選択
まずは自分の状況(学歴、年齢、経済状況)を整理し、「専門学校ルート」か「実務経験ルート」か、大きな方針を決めましょう。
2. ルート別アクション
- 専門学校ルートの場合: 複数の専門学校の資料を取り寄せ、オープンキャンパスに参加する。
- 実務経験ルートの場合: 工場求人ワールドで「未経験OK」「資格取得支援あり」の整備士求人を探し、働きながら学べる環境を見つける。
3. 学習計画を立てる
試験日から逆算して、無理のない学習スケジュールを立てましょう。(例:試験6ヶ月前からテキスト開始 → 3ヶ月前から過去問演習…など)
自動車整備士は、やりがい・安定・将来性のすべてを備えた国家資格です。まずは、資料請求か求人チェックから「一歩目」を踏み出してみましょう。工場求人ワールドは、その挑戦を全力でサポートします。