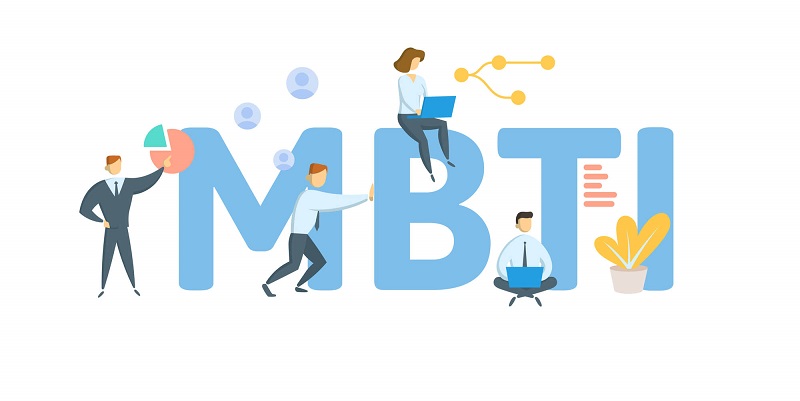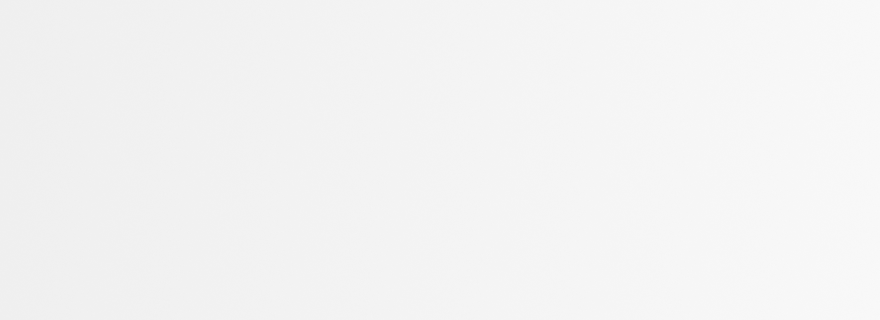目次
鋳物工場(いものこうじょう)とは、溶かした金属を型に流し込み、さまざまな製品を作る工場のことです。
本記事では、鋳物工場の仕事内容や身近で使われる鋳物製品の例、代表的な鋳造方法などをわかりやすく解説します。日本は鋳物の生産量が世界でも上位に位置するなど、国内には長い歴史を持つ鋳物工場が数多くあります。鋳物製品は自動車のエンジン部品や家電、日用品など幅広い分野で使われ、私たちの生活を支えています。
本記事を読むことで、鋳物工場の仕組みや鋳造方法の特徴を理解し、求人の探し方や関連する金属加工技術まで幅広く学べます。鋳物の奥深い世界を、一緒にのぞいてみましょう。
鋳物工場とは

鋳物工場では、金属を高温で溶かし、型に流し込んで冷やし固める作業が行われます。金属加工には鍛造や切削などさまざまな方法がありますが、複雑な形状を短期間で大量生産できる点で、鋳造は非常に重要な技術といえます。
国内の鋳物工場では、鉄やアルミなどのリサイクル原料を活用し、環境に配慮しながら高品質で効率的な製造を行うケースが増えています。また、産業用機械や自動車部品といった大型製品から、家庭用の調理器具まで幅広い鋳物製品をつくることができます。
身の回りで使われる鋳物製品の例
鋳物製品は私たちの身近なところで多く使われており、日常生活のさまざまな場面で活躍しています。下記は、身の回りで使われている鋳物製品の一例です。
- 自動車エンジンの部品
- 調理器具(鉄鍋、フライパン)
- 水道の蛇口
- マンホールの蓋
- 橋やフェンス
これらの製品は、金属を圧力や重力で型に流し込んで成形するため、複雑な形状でも比較的容易に大量生産できるのが特徴です。
鋳物製品の特徴とメリット
鋳物製品は、形の自由度が高く、強度と量産性を両立できる点が大きな特徴です。金属を型に流し込むため、複雑な形状の部品でも一度の工程で成形でき、加工コストを抑えながら高精度な製品づくりが可能になります。
鋳物工場の主な仕事内容

鋳物工場の主な仕事内容を、工程ごとの特徴や必要なスキルとあわせて紹介します。
鋳込み作業
鋳込み作業は、溶かした金属を型に正確に注ぎ込み、成形を行う工程です。作業者は炉で溶解された金属の温度を確認しながら、適切な速度と角度で流し込む必要があります。高温の液体金属を扱うため、耐熱手袋や防護服の着用、安全規定の遵守が欠かせません。
型枠外し作業
型枠外し作業は、冷えて固まった鋳物を型から取り出す工程で、製品の形状を損なわないよう慎重に行います。砂型では振動装置やエアブローで砂を除去し、金型では専用の機械や工具で開閉を行います。
細部まで不良や欠けがないかを確認することも重要で、この段階での発見は後工程の修正や品質管理の改善につながります。
混練機オペレーター作業
混練機では、鋳型の造型に使う砂や結合剤を混ぜ合わせ、型づくりに適した状態の型砂を作ります。配合が正確でないと、鋳物の寸法精度や表面の仕上がりに悪影響が出るため、オペレーターには材料特性を理解する力が求められます。混練機の運転状況を監視し、状況に応じて調整を行うことで、鋳造に適した均一な型砂を安定供給できます。
その他の工程(仕上げ・検査・出荷)
鋳物製品は鋳込み・型枠外しの後に、仕上げや検査、出荷といった工程を経て完成します。バリ取りや研磨などの仕上げ工程では製品の外観を整え、検査では寸法や欠けを確認します。最終的に品質基準を満たした製品のみが出荷されるため、正確さと丁寧さが求められる重要な工程です。
鋳物工場の仕事はきつい?危険性と安全対策

鋳物工場の仕事は、熱や重さを扱うため「きつい」と感じる人も少なくありません。ただし、近年では設備の自動化や安全対策が進み、昔に比べて作業環境は大きく改善されています。実際には「危険」「つらい」というイメージだけでは語れない、やりがいのある現場です。
鋳物工場の現場環境(熱・騒音・匂い)
鋳物工場では、金属を溶かす炉の近くで作業を行うため、夏場は特に高温になります。そのため、空調や換気システムを導入して作業環境を整える工場が増えています。
また、金属の溶解時に発生する音や匂いも特徴の一つです。最近では防音壁の設置や集じん機の導入など、作業者の負担を軽減するための対策が取られています。安全装備の着用を徹底すれば、健康面のリスクは最小限に抑えられます。
事故防止と安全管理の取り組み
鋳物工場では、火傷や転倒といった事故を防ぐために、安全教育と定期点検が欠かせません。作業開始前のミーティングで危険箇所を共有したり、作業手順を明確にする「ヒヤリハット活動」を行ったりする企業も多くあります。
さらに、耐熱服・安全靴・フェイスシールドなどの個人保護具(PPE)の支給や、作業エリアの区分けなど、現場全体で事故を防ぐ仕組みが整えられています。こうした取り組みにより、重大事故の発生率は年々減少しています。
鋳物工場で働く人の特徴と仕事のやりがい
鋳物工場では、集中力とチームワークを大切にしながら作業を進める人が多く働いています。工程ごとに協力し合うことで、複雑な製品を形にしていく達成感があります。
体力や注意力が求められる仕事ではありますが、自分の手でものづくりを支える実感を得られる点が大きな魅力です。熟練作業者の中には、技術を磨いてリーダーや検査担当にステップアップする人も多く、経験を積むことでキャリアを築ける環境です。
鋳物工場で役立つ資格やスキル

鋳物工場では、金属の運搬や型の操作など、機械を扱う作業が多くあります。資格を取得しておくと業務の幅が広がり、採用や昇進の際にも有利に働きます。
ここでは、鋳物工場で役立つ代表的な資格と、未経験から挑戦しやすい資格を紹介します。
必要・推奨される資格(玉掛け/フォークリフト/クレーン)
鋳物工場では、重量物を安全に移動させるために、玉掛け技能講習・フォークリフト運転技能講習・クレーン運転士免許などが重視されます。これらは作業の安全性を確保するために法律で定められた資格であり、取得者は現場で即戦力として活躍できます。
その他にも、溶接技能者資格や危険物取扱者乙種などがあると、業務範囲を広げやすくなります。資格の種類によっては企業が費用を負担してくれるケースもあるため、入社前に確認しておくと安心です。
未経験者におすすめの資格と取り方
未経験から鋳物工場の仕事を目指す場合、フォークリフト運転技能講習や玉掛け技能講習の受講から始めるのがおすすめです。これらは比較的短期間(2〜3日程度)で取得でき、全国の安全衛生教育センターや認定機関で受講可能です。
また、入社後に会社が講習を手配してくれるケースも多いため、焦って資格を取る必要はありません。まずは興味のある職種に応募し、実際の業務内容を理解したうえでステップアップしていくのが現実的です。
【関連記事】工場など製造業におすすめの資格ランキング
代表的な9つの鋳造方法

鋳造にはさまざまな方法があり、それぞれに特徴や適用分野が異なります。鋳造方法は製品の形状やサイズ、生産数によって最適なものが異なります。たとえば少量生産で複雑な形状を求める場合と、大量生産で安定品質を求める場合とでは、最適な鋳造方法が異なります。
ここではよく使われる9つの方法を詳しく見てみましょう。
1. 砂型鋳造法
砂型鋳造法は、最も古くからある代表的な方法で、多様な金属や形状に対応しやすいのが特徴です。砂型は使い捨てとなることが多いですが、大型製品から小型部品まで幅広く対応できます。金型よりもコストが低いことが多いため、小ロット生産や自由度の高い形状の鋳造に向いています。
2. 重力金型鋳造法
重力金型鋳造法は、あらかじめ作られた金型に溶融金属を自然の重力のみで流し込む方式です。金型自体の精度が高いため、量産に向いており、表面が比較的きれいに仕上がるのが利点です。ただし、金型製作にコストがかかるため、大量生産に向いた手法です。
3. 低圧鋳造法
低圧鋳造法は、溶融金属に低い圧力をかけ、下部から上方向へ型に注入する方法です。金属の流れが安定し、気泡や偏りが少なくなることで、均一な品質を得やすいのが特徴となります。また、比較的薄肉の製品でも安定して成形しやすいため、自動車や家電の精密部品などにも活用されています。
4. 高圧鋳造法
高圧鋳造法は、高圧で溶融金属を型に一気に射出する方法です。短時間で薄肉の複雑な形状を大量生産でき、均質な組織の製品が得られる利点があります。一方、設備コストが高いことや、金型のメンテナンスが必要になる点にも注意が必要です。
5. ダイカスト法
ダイカスト法は、高圧鋳造法の中でも代表的な手法の一つで、特にアルミや亜鉛など融点の比較的低い金属に用いられます。自動車のエンジン部品や家電製品など、多岐にわたる領域で利用されており、薄肉かつ精密な部品を効率良く量産することが可能です。
6. ロストワックス精密鋳造法
ロストワックス精密鋳造法は、ワックスで細部まで形状を再現した原型を作り、それをセラミックなどで覆って型を作る方法です。加熱時にワックスが溶け出して空洞ができ、この空洞に金属を流し込む仕組みです。複雑な形状と高い寸法精度を両立できるため、航空機や医療機器の部品など、高精度が求められる分野で活用されています。
7. 遠心鋳造法
遠心鋳造法は、回転による遠心力を利用して金属を型の外周部分に押し付ける方法です。パイプや円筒形状など、回転対称の製品を成形するのに適しており、内壁が滑らかな部品を比較的容易に製作できます。主に水道管などの筒状部品で使われる技術です。
8. 連続鋳造法
連続鋳造法は、溶融した金属を連続的に型に送り込みながら冷却固化させ、同時に引き抜いていく方法です。棒材や板材など長尺物の大量生産に向いており、鋼板や鋼線などの素材製造で広く採用されています。材料のロスが少なく、生産効率にも優れています。
9. 消失模型鋳造法
消失模型鋳造法は、発泡スチロールなどの発泡材で作った模型を砂型で埋め、そこへ溶融金属を注入する方法です。発泡材が金属の熱で消えてなくなるため、複雑な形状でも型崩れを起こしにくい利点があります。余分な分割が必要ないことから、部品を一体で鋳造できるため、工程の削減や高効率な製造につながります。
鋳物以外の金属加工技術とは

金属加工には鋳造のほかにもさまざまな方法があり、それぞれに異なる特徴や用途があります。製品の機能や用途、製造コストなどに応じて、最適な加工技術が使い分けられます。以下では、鋳物以外の金属加工技術を紹介します。
鍛造
鍛造は、金属に強い圧力や衝撃を加えて成形する加工方法です。金属組織が鍛えられることで強度や耐久性が向上し、自動車のクランクシャフトや航空機の重要部品など、高いな強度が求められるパーツにも用いられます。
ただし、複雑な形状の製品には不向きであり、大型の機械設備が必要になる場合も多いため、コスト面の考慮が必要です。
切削
切削は、旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて金属の不要部分を削り取り、目的の形状に仕上げる手段です。高い精度が得られる一方で、削りカスが発生するため材料の使用効率はやや低下します。
主に最終調整や高精度部品の製作で利用され、少量多品種の部品製造に適しています。
溶接・溶断
溶接は複数の金属部品を接合する技術で、溶断は不要部分を熱で切り離す加工です。自動車のボディや建築構造など、大小さまざまな製品の組立工程において重要な役割を持ちます。製品の強度や見た目の仕上がりにも大きく影響するため、溶接工には熟練の技術と経験が求められる分野です。
【関連記事】溶接作業の種類や手順・やり方のコツを紹介!溶接機の使い方と注意点も解説
未経験・女性でも働ける?鋳物工場の働き方

鋳物工場は「体力仕事」というイメージを持たれがちですが、近年は自動化や分業が進み、未経験者や女性も活躍できる職場が増えています。
ここでは、どんな仕事から始められるのか、そして働きやすい環境づくりの取り組みについて紹介します。
未経験からでもできる仕事内容
未経験者は、まず補助作業や検査業務などからスタートするのが一般的です。型の清掃、製品の仕上げ、梱包など、専門的な知識がなくてもできる工程が多くあります。
また、先輩作業員のサポートを受けながら作業を覚えられるため、少しずつ技能を身につけていけます。丁寧な指導体制を持つ工場も多く、経験がなくても安心して働ける環境が整っています。
女性が働くための工夫やサポート
女性作業員が働きやすいよう、軽作業を中心に担当できる配置や、機械操作の自動化が進んでいます。さらに、近年では育児休暇や短時間勤務制度を導入する企業も増えており、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
体力面に不安がある人でも、作業負担を軽減する補助機器(リフト・アシストスーツなど)を導入している工場もあり、安心して長く続けやすい職場環境が整いつつあります。
【関連記事】工場勤務の女性あるある10選!人気のある業務や意外と多い悩みを紹介
教育・研修制度の例
多くの鋳物工場では、入社後に安全教育や基本作業研修を行い、未経験者が基礎から学べるようサポートしています。技能講習や外部研修を受ける機会を設けている企業もあり、資格取得支援制度を利用してステップアップする人も少なくありません。
こうした教育体制が整っていることで、働きながら着実に技術を身につけ、キャリアを築くことができます。
鋳物工場の平均年収と待遇
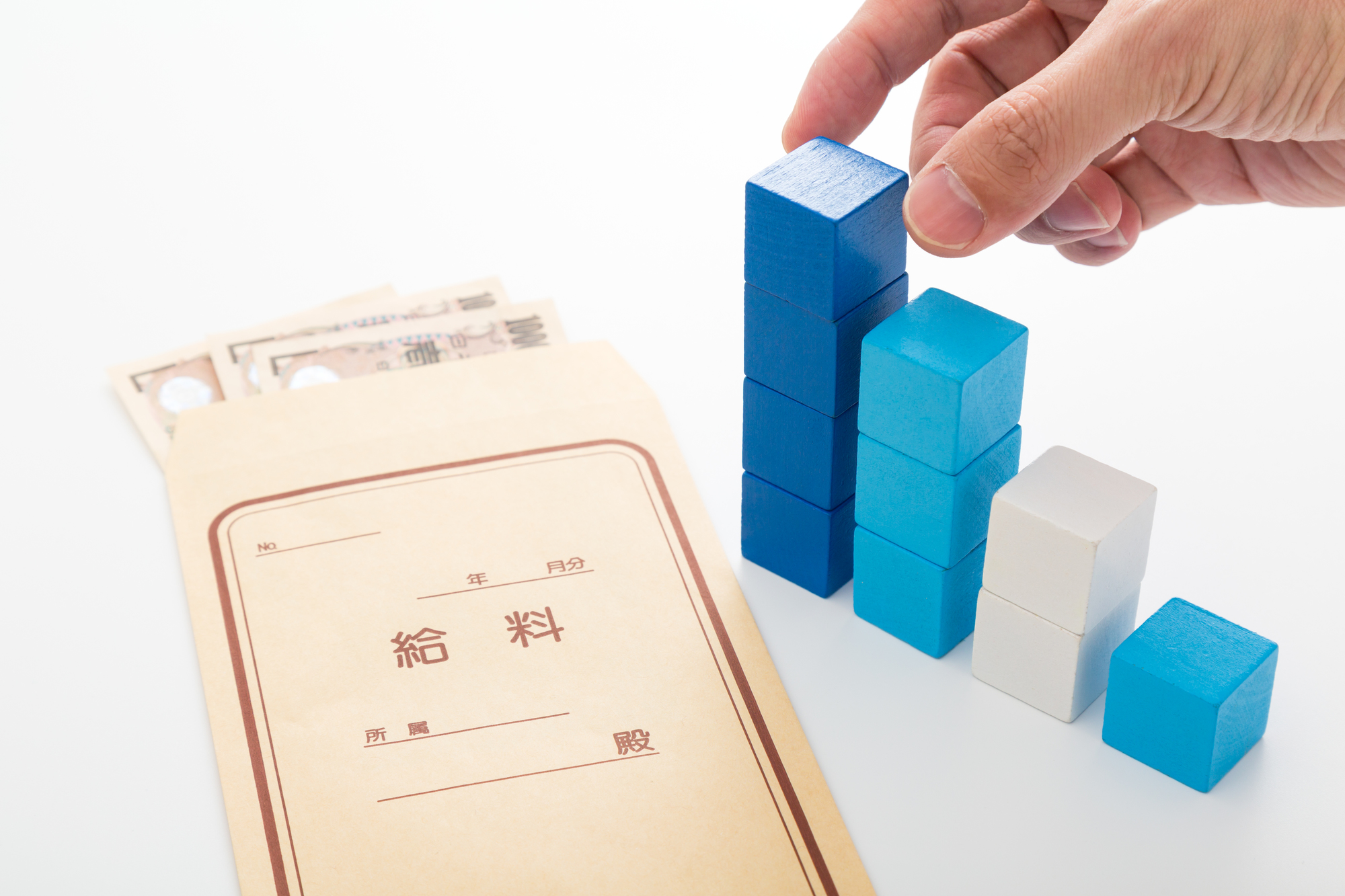
鋳物工場の給与水準は、地域・企業規模・経験年数によって異なります。ここでは、平均的な年収の目安や待遇面について紹介します。
平均年収の目安(地域・企業規模別)
一般的に、鋳物工場で働く作業員の平均年収は350万〜450万円程度が目安です。中小企業ではやや低めの水準になる一方、大手メーカーや専門技術職では500万円を超えるケースもあります。
地域別に見ると、製造業が盛んな愛知・静岡・群馬・広島などでは比較的高い傾向があります。
賞与・福利厚生・手当の有無
多くの鋳物工場では、基本給に加えて賞与(年2回)や各種手当(通勤・残業・家族手当など)が支給されます。住宅補助や退職金制度を設けている企業もあり、安定した収入基盤を築きやすい環境です。
さらに、資格手当や安全作業奨励金など、日々の努力が反映される仕組みを採用する企業も増えています。
給与アップを目指すポイント
給与を上げるためには、技能講習の受講や資格取得を通じて専門性を高めることが重要です。玉掛けやクレーン運転士などの資格を持つ人材は、安全管理者や現場リーダーなどへの昇格チャンスが広がります。
また、製造工程全体の知識を身につけると、検査・品質管理・生産計画など、事務系の管理職にステップアップする道も開けます。
鋳物工場の将来性とキャリアパス

鋳物産業は長い歴史を持ちつつも、技術革新によって進化を続けています。AIや自動化技術の導入が進む中で、今後の働き方やキャリアの可能性も広がっています。
業界の動向と今後の展望
近年、鋳物工場では省エネルギー化・環境対応・自動化が進み、より安全で効率的な生産体制へ移行しています。国内では人材不足が課題ですが、技能継承とデジタル化が両立しつつあり、安定した需要が見込まれます。
特に自動車やインフラ分野では、軽量化素材や新合金の研究が進んでおり、今後も一定の需要が続くと予想されています。
ステップアップできる職種・資格
経験を積むことで、ラインリーダー・品質管理者・生産管理担当など、より責任のあるポジションにステップアップできます。さらに、技能士資格や安全衛生責任者などの資格を取得することで、キャリアの幅が広がります。
また、海外生産拠点を持つ企業では、現場監督や技術指導者として活躍するチャンスもあります。
長く働くためのポイント
長く働くためには、安全意識とチームワークを大切にすることが欠かせません。無理のない働き方を意識し、定期的に体調を整えることも大切です。
また、技術を磨き続けることで、年齢を重ねても活躍できる分野です。変化する製造技術に関心を持ち続けることが、安定したキャリアを築く鍵になります。
鋳物工場の求人の探し方

鋳物工場で働くには、現場作業のノウハウや安全への意識が強く求められます。技術習得には時間がかかるものの、経験を積むことで専門性が高まり、安定した収入を得られる職種です。
以下に挙げる3つの求人探しの方法をうまく組み合わせて、自分に合った環境で鋳物の仕事に挑戦してみましょう。
ハローワークを利用する
地域の求人情報が集まる公的機関であるハローワークでは、地域密着型の鋳物工場の求人を見つけやすい傾向にあります。地元の企業と直接やり取りができるので、職場環境や応募条件の詳細を相談しやすい点が魅力です。
特に中小規模の鋳物工場では、インターネット上に求人を出していないケースも多く、ハローワークを活用することでより多くの情報を得られます。
【関連記事】ハローワーク応募の流れを徹底解説|登録から面接成功までの完全ガイド
工場・製造業に特化した求人サイトを利用する
工場や製造業に特化した求人サイトでは、職種や勤務条件、勤務地などの情報を細かく絞り込んで検索できるのが利点です。作業内容の詳細やスキル要件が明記されている場合が多く、自分に合った求人を短時間で絞り込みやすくなります。
また、工場見学が可能な求人も掲載されていることがあるため、実際の現場を見たうえで応募を検討できる点も魅力です。
工場求人ワールドでは、工場・製造業に特化した求人を多数掲載しています。「未経験から工場に挑戦したい」「高収入の仕事を探している」という方は、工場求人ワールドで検索してみてください。
知人・友人に紹介してもらう
鋳物工場で働いている知人や友人に紹介してもらう方法は、職場の雰囲気や働き方を事前に知ることができるため安心です。求人サイトにはない細かな情報や、リアルな現場の声を参考にできるのもメリットでしょう。
また、紹介であれば企業側も採用プロセスをスムーズに進められる場合が多く、面接前にお互いの期待値を調整しやすい傾向にあります。
気になる鋳物工場に直接訪問する
近隣の鋳物工場に直接足を運び、求人の有無を確認する方法も有効です。小規模な工場では求人を公開していない場合もあり、実際に訪問することで思わぬチャンスに出会えることがあります。
また、現場を直接見ることで作業環境や職場の雰囲気を確かめられ、自分に合うかどうか判断しやすくなります。特に地元で長く働きたい人にとっては、職場との距離感をつかむ良いきっかけになるでしょう。
よくある質問

Q1.「鋳物工場」の読み方は?
A1.鋳物工場は「いものこうじょう」と読みます。鋳物は「いもの」と読み、金属を溶かして型に流し込む加工技術を指します。
Q2.鋳物工の平均年収はいくら?
A2.鋳物工の平均年収はおおよそ382万~501万円です。
企業規模や経験年数、保有資格などによって変動しますが、製造業の中では比較的高水準です。高温の金属を扱うため特殊な技能や安全管理が求められ、技術力の高い人材が重視される傾向にあります。
※参照:給料BANK
Q3.鋳物工場は危険ですか?
A3.鋳物工場は高温の金属を扱うため、火傷や転倒などのリスクはあります。
ただし、現在では安全装備(耐熱服・手袋・ヘルメット)の支給や、作業マニュアルの徹底、安全教育が行われており、事故は大幅に減少しています。正しい知識と装備を身につければ、危険を最小限に抑えて働くことが可能です。
Q4.未経験でも働けますか?
A4.はい。鋳物工場では、未経験者を対象にした研修制度やサポート体制を整えている企業が多くあります。
最初は補助作業や検査などの軽作業からスタートできるため、専門知識がなくても安心して働けます。経験を積むことで、より高度な工程や機械操作を任されるようになります。
Q5.鋳物工場で取っておくべき資格は?
A5.鋳物工場で役立つ資格には、玉掛け技能講習・クレーン運転士・フォークリフト運転技能講習などがあります。これらを取得しておくと、安全管理や製品搬送などの作業を任されやすくなり、昇給・昇格にもつながります。企業によっては資格取得支援制度があり、働きながら取得を目指すことも可能です。
Q6.鋳物工場は将来性がありますか?
A6.鋳物産業は、国内の製造業を支える基幹分野のひとつです。自動車や建設、エネルギー設備など幅広い産業で需要が続いており、今後も安定したニーズが見込まれます。
さらに、AIや自動化技術の導入が進むことで、作業効率や安全性が向上し、新しい働き方も広がっています。技術を磨き続ければ、将来的にも長く活躍できる分野です。
まとめ
ここまで、鋳物工場の概要から代表的な鋳造方法、求人の探し方までを包括的に解説しました。鋳物は日常生活のあらゆる場面で使われており、ものづくりを支える奥深い金属加工技術です。
鋳物工場の仕事に興味がある人は、まず工場見学や求人検索を通して現場の雰囲気を確かめてみましょう。自分に合った職場が見つかれば、専門性を磨きながら長く安定したキャリアを築くことができます。
工場求人ワールドでは、工場の求人情報を豊富に取り揃えています。安定した職場で働きたい、高収入の仕事を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。